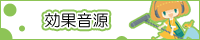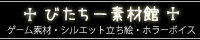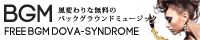用語集
|
|
キョンシー
|
中国にいるゾンビ。人を吸血し、自分の仲間にするところは吸血鬼に似てい る。 皮膚が硬く、普通の銃弾を貫通しないらしい。また、満月の晩には凶暴にな る。 退治方法としては、桃剣か銭剣などで強制的に切り伏せるか、お札を使って 使役し、その後に浄化の儀式を行って冥府に送る事で退治できる。 |
霊幻道士
|
中国で悪さをするキョンシーを退治したりなど、魔を滅する力を有した霊能力者。 道具として主な物は以下の通り。 ・桃剣:古くから魔を祓う力があると言われる桃の木から切り出した木刀。丁寧に清められ、霊力の伝導率をよくしてある。 ・銭剣:金銭剣ともいう。法具的な面もあるが、霊力を込めると強力な剣になる。魔を捕縛する道具としても使用できる。 ・お札:主にキョンシーを操ったり、炎を出現させてキョンシーを燃やしたりなど多種多様に扱える。 ・ 鐘:お札を貼り付けたキョンシーを操るための法具。 |
師匠=スースー
|
これは、中国などで師匠に敬意を払っていう言い方。言い方としては、空気を抜くような感じでいうのがコツ。 |
テンテン師匠語録
|
|
| 人に八疵あり | 荘子の中にある言葉で、人には八つの欠点があると言われ、ひとつずつが総(そう)・佞(ねい)・諂(てん)・諛(ゆ)・讒(ざん)・賊(ぞく)・匿(とく)・険(けん)と呼ばれている。 「人に八疵あり、事に四患あり」のセットで使われる事もある。 事に四患ありというのも欠点のような物を表した語句で、人の中にある悪い性格を表していると考えられる。 八つの欠点の意味は以下の通り。 |
八つの欠点の意味
|
|
| 総(そう) | 自分のしなくてよいことまでしてしまうこと |
| 佞(ねい) | 相手の聞きたくもない話を、いつまでもくどくど話すこと |
| 諂(てん) | 相手の顔色をうかがって、相手が喜ぶ話をすること |
| 諛(ゆ) | 良い悪いのおかまいなしに、その場限りの話をすること |
| 讒(ざん) | 好んで人の悪口を言うこと |
| 賊(ぞく) | 人との交わりをやめ、人から離れること |
| 匿(とく) | 自分の機嫌をとる者を誉め、自分の嫌いな者を遠ざけること |
| 険(けん) | 善悪を見きわめず、両方に調子よくふるまうこと |
四患
|
|
| 叨(とう) | 大きな事をしたがり、功名を求めること |
| 貪(ひん) | 自分が正しいと疑わず、自分の意見を押し通して人をおしのけ、でしゃばること |
| 狠(ろう) | 自分の過ちがわかっていても改めず、人が注意するとますますガンコになること |
| 矜(ぎん) | 自分と同じ意見を良いと思い、自分と違う意見を悪いと思うこと |
勝つべからざるは守るなり。勝つべきは攻むるなり
|
|
| 孫子の中にある言葉で、勝てる条件がなければ守りを固め、勝てる条件があれば攻める事がいいという言葉。 一か八かな戦いより、安全で、かつ完全勝利を目指すのならば十分な力を持って攻めるのが確実であり、不足していると感じたら守りを固めて機をうかがう事が大事だということだと言っている。 つまり、状況の変化を見て動き、勝てる条件が整った状況に対応していけば勝利を見つけられるという事なのかもしれない。 |
|
| 敬(けい)せられざるに至(いた)れるは、これわが徳修(とくおさ)まらざるなり | |
| 史記の中にある言葉で、相手から敬意をもたれないのは、自分のほうにも敬意をもたれるだけのものがないからだという言葉。 つまり、あまく見られるのは自分にも原因があり、まだまだ自分も未熟だということを戒める言葉なのかもしれない。 |
|

キャスト

テンテン:小野寺 さな

灯劾:モ。
(とうがい)

灯書文:YUITO
(とうしょぶん)

那瀬 鏡志郎:伊吹雪那
(なぜ きょうしろう)

那瀬 紅華:月詠白雅擘
(なぜ こうが)

基山 美優:りおか
(きやま みゆ)
 りんく
りんく
|
吉田史記さんの声+竜門さんの声を借りました。
|
|